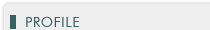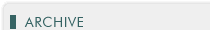みんな、最初は、ぜんぜんだめだった。。
宮台真司さんの巻。
09/06/25
インターネットも
携帯電話も
消費税もなかった、
大学の1、2年生のころ。
家庭教師のアルバイトをしていたことがあります。
小田急相模原駅前の
富士銀行の中にあったホワイトボードの掲示板に
「家庭教師 週1回 月2万1000円 体育も教えます」
とインフォメーションしたのがきっかけでした。
「月2万1000円」というのは
わたしの6畳1間のアパートの家賃。
「体育も教えます」というのは、
わたしのセールスポイントのアピール。
同じ掲示板で家庭教師の案内をしていた
他の学生たちの大学名が一流どころばかりなので、
彼らとは差別化しなければと思い、
「体育も~」の一文をひねりだしたのでした。
すると、
まもなくアパートの黒電話が鳴りまして。
サッカークラブでフォワードをやっていて、
学校では2番目にかけっこが速いという
5年生の男の子の家庭教師になることができたんです。
で、
初めての「授業」。
いまでもよく憶えています。
2階の部屋にノックして入ると、
わたしの座る椅子が学習机のそばに準備してあり、
机の上には算数の教科書とノートが開いてあり、
その机に向かって男の子が緊張した様子で座っていました。
当時のわたしは
夜な夜な車を飛ばして友だちと大磯あたりまで出かけたり、
徒歩3分の銭湯にその車で通ったり(風呂なしアパートでした)、
ちゃらんぽらんの極みの大学生でしたので、
家庭教師についても「受注」できただけでこれ幸い。
とくだんの心の準備もないまま、
初日に臨んだ次第です。
ですので、
男の子の緊張した様子を見たとたん、
わたし、
輪をかけて緊張してしまいまして。
勉強はじめる前に
なにはともあれ仲良しになろうと
「算数って解けたら面白いよ」
とか
「クラスのみんなと競争だね」
とか
声掛けたと思いますけど、
反応いまいち。。
どうしようかと頭をかかえたとき、
そうだ、
「体育も~」のセールスポイントを
いまこそ発揮してみようと思いつき、
男の子の目の前で腕まくりして、
エイヤッと力こぶを出したんですね。
男の子はパッと笑顔になりました。
それでわたし、
調子に乗ってシャツまでめくりあげ、
割れた腹筋も出してあげたのでした。
(現在では跡形もありませんが)
それをきっかけに打ち解けることができ、
「授業」もスムーズにいきました。
成績も伸びて、
お母さんからクリスマスにセーターもらったり、
男の子とはサッカーの練習も一緒にしたり、
じつに楽しく家庭教師をやらせてもらったんです。
男の子は
「どうしたら筋肉がつくの?」
と何度も聞き、
それに答えてわたしは
「勉強すれば筋肉つくよ」
と真顔で冗談を言ってました。
社会学者の宮台真司さんは
著書の『14歳からの社会学』(世界文化社、2008年)で
こんなことを書いてます。
ぼくたちがものを学ぼうとするときに、どういう理由があるだろう。まず1つ目に挙げられるのが「競争動機」(勝つ喜び)。周りの子とテストの点数を競い合うとか、人よりも高い偏差値の学校に合格したいと思って受験勉強をするのは、この「競争動機」による。/2つ目に挙げられるのが「理解動機」(わかる喜び)。「自分の力で問題が解けた」とか「自分の考えをうまく説明できた」と感じる喜びだ。戦後の日本の教育は「競争動機」と「理解動機」に集中して議論がなされてきた。だが、実はもう1つ大切な動機がある。/それが「自分もこういうスゴイ人になってみたい」と思う「感染動機」だ。直感で「スゴイ」と思う人がいて、その人のそばに行くと「感染」してしまい、身ぶりや手ぶりやしゃべり方までまねしてしまう――そうやって学んだことが一番身になるとぼくは思う。(『14歳からの社会学』132ページ)
ミュージシャンは優れたプレーヤーの演奏を徹底的にコピーして、やがて自分の演奏スタイルを作る。小説家だって同じだ。優れた作家の作品を徹底的に読み、文体模写なんかしながら、いつしか自分の作品世界を作る。学問だって同じ。大切なのは「感染」だ。/①誰かに「感染」して乗り移られたあと、②徹底的にその人の視点から理解し、③やがて卒業して今度は別の誰かに「感染」する――。①→②→③を数回くり返せば、そのときにはすでに君自身が、誰かから「感染」してもらえる価値を持つようになっているだろう。(『14歳からの社会学』139ページ)
筋肉をきっかけに
あの男の子は
家庭教師のわたしに「感染」してくれたんじゃないか
なんてことは思わないけど、
でも
わたしは男の子にとって「スゴイ大人」でなければと
「授業」へ出かける前には
腕立てと腹筋を欠かさなかったんです。
「授業」の準備もそこそこに
6畳のリビング兼ダイニング兼スリーピングルームで
筋トレをやっていた。
じゃあ「感染」するほど「スゴイ人」とは、
どういう人なのか。
宮台さんは
世間や親が「こういう大人が立派なんだ」というのとは、
次元が違う、と言います。
ぼくも親から「こういう大人が立派なんだぞ」といわれて信じこんでいた一時期がある。けれど、それは経験によって裏切られていった。ぼくの仲のよかった友だちのお父さんは、背中にクリカラモンモンをしょうヤクザだったけど、その人がらにふれて「スゴイ」と思った。(中略)クリカラモンモンのおじさんに、大人たちは眉をひそめていたけれど、ぼくにとっては、「スゴイ人」だった。見ると聞くとじゃ大違いで「感染」した。だから、ぼくはヤクザに偏見がない。そのことが、のちに中高生売春やクスリの調査をするときにも、ずいぶん役に立った。(『14歳からの社会学』144~145ページ)
子どものころ、
クリカラモンモンのおじさんに「感染」した宮台さん。
大学・大学院のころには
哲学者の廣松渉さん、社会学者で評論家の小室直樹さんに
「感染」したのだそうです。
彼らはぼくからすれば「この世ならざる存在」だ。そんな彼らに「感染」することで教養を身につけたぼくは、彼らに「感染」するときにこそ〈自由〉を感じていた。/ぼくは昔から「非日常体質」だった。早生まれで、体力も知力もおとり、学校でうまくやれなかったぼくは、屋上にのぼるのが好きで、お祭りが大好きだった。中学・高校ではアングラにハマった。いまでも、そういう「非日常」なものにふれるときにこそ〈自由〉を感じる。(『14歳からの社会学』191ページ)
「感染」するときこそ〈自由〉になる――。
むずかしいけど、わかるような気がします。
しかし
わたしは
だれか「スゴイ人」に「感染」したことが
あったのか?
うーん。。。
もしかして、嫁はん?
でも彼女とは〈自由〉よりも〈不自由〉を感じるし...。
「感染」の経験って
気づかずに過ぎることもあるんだ、きっと。
畑村洋太郎さんの巻。
09/04/23
新聞とかテレビで、毎日のように
頭ぺこぺこ下げてる人たちを目にします。
「男はあんまり頭ぺこぺこ下げるもんやない」って
高校時代、担任の先生(=レスリング部監督)から言われたものですが、
最近は、
会社のエライさんから芸能界のスターさんまで、
不祥事やら逮捕やら
ぺこぺこのオンパレードであります。。
昔も、こんなだったっけかなあ?
謝罪会見なんて、
高校時代(=30年前)に見た覚え、あんまりないんだけど。
今の世の中、
ミスったときは速攻でぺこぺこしないと
誰も許してくれないんでしょうか。
キツイなあと思います。
わたしも
失敗とか粗相したときは「すみません」と
すぐにぺこぺこするほうですが、
気分が落ち着かないうちにぺこぺこしてしまうと
なお気分が落ち込んじゃいますよ。
落ち込んでいるときに
メディアで責任追及され
謝罪会見に引っ張り出されてのぺこぺこは
キツイでしょうねえ。
そんなあわてて会見しなくても
しばらく時間を置いて
もろもろ落ち着いてから改めてぺこぺこしてもらえば
わたし的には全然OKじゃないかと思うんですけど。
たとえば企業不祥事が起きると
よく危機管理のコンサルタントとかいう人たちが出てきて、
謝罪の仕方なんかについてあれこれ言いますが、
会社のイメージダウンを防ぐためにどう謝るか
という視点からの話が多くて。
会見でペコペコ謝る人のストレスには
目が向いてないんだもん。
「失敗学」で有名な畑村洋太郎さんは
こんなこと言ってます。
程度に差はありますが、失敗したときには誰だってショックを受けるし傷つきます。本人は気づかないかもしれませんが、直後はエネルギーが漏れてガス欠状態になっています。こういうときに失敗とちゃんと向き合い、きちんとした対応をしようとしても、よい結果は得られません。大切なのは「人(自分)は弱い」ということを認めることです。自分が、いまはまだ失敗に立ち向かえない状態にあることを潔く受け入れて、そのうえでエネルギーが自然に回復するのを待つしかないのです。/不思議なもので、人はエネルギーが戻ってくると、困難なことにも自然と立ち向かっていけるようになります。これは人間がもともと持っている「回復力」の為せる業です。
『回復力』(講談社現代新書)34ページ
こないだ
ホームレスの方々の自立支援してる人を取材したんですけど、
その人も、
畑村さんと同じようなこと言ってました。
路上生活に困窮した人を
シェルターへ入れてあげると
「申し訳ない、すぐに仕事さがしますから」
と恐縮するんですって。
でも、その人は、
「いかんいかん、まず休め」
と諭して、
しばらくエネルギー充電させると。
苦しいときにも頑張って、一時的に無理をするというのは、確かに窮地から脱するひとつの方法です。ただし、この方法が使えるのは自分にまだエネルギーが残っているときに限られます。エネルギーがないときに頑張ろうとするのは、勝つ見込みの薄いギャンブルに身を預けるようなものです。エネルギーがそれほど残っていないのに、自分に負荷をかけ続けたら、あっという間にエネルギーがなくなってしまいます。その挙げ句、潰れて再起不能になっている人は現実にはたくさんいます。
『回復力』37ページ
畑村さんは、
エネルギーが回復するまで
苦しい場面から逃げ出したり、
失敗をしょうがないと考えたり、
人のせいにしたりしてもいい、
ということも本のなかで言ってます。
間違ったり、
失敗したりしない人なんて
どこにもいないし、
自分だってぺこぺこしなきゃいかんことを
いつ起こすかしれないんですからね。
人が失敗して
エネルギーダウンしてるときに
謝罪会見やれとか追及するのって、
いかがなものでしょう。
それにしても
畑村さんの「失敗学」ってすごいなあと
思います。
『回復力』のほかにも
畑村さん本、何冊も読みましたが、
いろんなこと教えてくれますよ。
畑村さん、
失敗との付き合い方を考えるうえで、
ベースになった出来事があるんだそうです。
私がまだ東大工学部の講師をしていた一九七〇年代のはじめのことです。/校舎内でお昼ご飯を食べているときのこと、突然、窓の外を大きな黒い影がさっと落下していくのが見えました。「えっ」と、びっくりした瞬間、続いて「ドスン」という何とも言えない重苦しい音が響きました。影の正体は飛び降り自殺をはかった学生でした。
『回復力』12ページ
当時、学生の自殺は社会現象になるほど多く、
東大工学部でも複数あったそうです。
自殺をはかった学生の大半は
うつ病を患っていたと知った畑村さん、
専門家に学び、
対応策を講じます。
そして
うつへの対応が
失敗との付き合い方を考えるベースになりました。
失敗が原因でうつになる人は大勢います。とくにそれが大きな失敗の場合、その人のふだんの性格などに関係なく、誰でもうつになる可能性があります。そうした場合は、周りも細心の注意を払う必要があるし、本人もそれを自覚して動かないと取り返しがつかなくなる場合があります。
『回復力』21ページ
これは肝に銘じておかないと。
けっこう怖いご指摘です。。
足立倫行さんの巻。
09/03/26
中学・高校のころ。
「取材」というのはハードルの高い仕事で、
なんというか、
物事の本質を見抜く能力があって、
かつ、
ずうずうしいぐらいの性格を持つ人でないと
できないんじゃないかと思ってました。
わたしの頭の中では、
取材をする人といえば政治記者とか事件記者で、
いつも夜討ち朝駆けでスクープを狙ってる、
みたいなイメージだったんです。
で、
大人になって、
出版社に入ったところ......。
夏の盛りに、
月刊誌の女性編集者が
ひらひらのワンピースで、
かつ、
日傘片手に、
「取材、行ってきまーす」と
オフィスを出発していきました。。
すごい衝撃でした。
ああ、取材って、
あんな格好でも、
誰でもOKなのか。
ありふれた仕事なんだ!
新聞とか週刊誌の記者じゃなくても、
語学雑誌やウエブサイトの編集者だって
単行本や企業PR誌のライターさんだって
小学校の広報誌を作るPTAのママさんだって、
いろんな人が取材してるのでした。
実力イマイチのライターさんなんかにかぎって、
取材がどうの、仕事がこうのと、
複雑なウンチクくださることもありますが、
べつに取材って誰でもやってるし、
できることなんですよね。
とはいえ、やっぱり、中高生時代に抱いたイメージは強いのか、
今でもわたし、
とくに取材旅行へ出発する日は
朝から落ち着かないんです。。
うまくいかなかったらどうしよう、
また遠くまで出かける時間もお金もないし、
自分なんかの取材で大丈夫なのかと、
あれこれ考えてしまうんです。
ノンフィクション作家の足立倫行さんも
こんなこと書いてます。
フリーの物書きになって13年目、
「最低でも月に一・二回は取材旅行に出て」いたころに
書かれた文章です。
最寄り駅に向かう途上はいつも気分が重い。電車内では必ず腹具合が悪くなり、駅や空港に到着するやいなやトイレに駆け込む。尾籠な話だが決まって下痢をする。何もかもいやになり、そのまま回れ右して家に帰りたくなる。実に情けなく、心細い精神状態なのだ。(『人、旅に暮らす』現代教養文庫・1993年・313ページ「シリーズのためのあとがき」)
このころの足立さんは
『人、旅に暮らす』のほかにも
『日本海のイカ』(情報センター出版局・1985年)
という大宅壮一ノンフィクション賞候補になった本も書いていて、
すでに名うてのノンフィクションライターさんでした。
なのに、
まだ取材旅行には。。。
駅のトイレに駆け込むのは
わたしと同じであります。
でも、
いったん取材のスケジュールに乗ってしまうと、
足立さん、
「急に蘇生する」んです!
......僕もいっぱしの"職業としての旅人"に変貌する。好奇心を最大限にまで膨らませながら油断なく、素速く、精力的に行動する。少々の危険は厭わないし、面倒で複雑なこともあえて避けようとはしない。机の前で置物のように坐ったきり動かないふだんの自分を考えると、我ながら別人のようだと思う。そして、能力の限界に挑戦するようなそうした取材の旅から自宅に戻ってくると、ドッと疲れ、しばらくは痴呆のごとく眠るだけなのである。(中略)毎月何度も家を離れ、自分が興味を抱いた対象を納得のゆくまで追い駆けるようになって初めて、僕は取材の旅が一期一会の真剣勝負だと思い知らされるようになったのだ。(『人、旅に暮らす』315ページ)
取材がはじまってもダメダメなわたしとちがって、
さすが、一流のノンフィクションライターさんです。
『人、旅に暮らす』という作品は、
競輪選手や養蜂家やプロ球団スカウトなど、
旅をしながら仕事をしている人たちをルポしたものです。
週刊誌の記者を辞めて、
フリーの物書きになった足立さんの
最初の作品なんだそうです。
これは僕にとっては処女作だった。誰にとっても最初の作品というのは、さまざまな思い出と愛着があり、たとえ未熟でも忘れがたいものだろうが、僕の場合も同様である。/何年か若者向け週刊誌の取材記者をやってきて、どうにも苦しくなって辞めたものの、展望はなかった。三十歳を過ぎて、妻子があって、まったくの無名だった。フリーのルポライターの看板を掲げたのはいいが、仕事らしい仕事の依頼はほとんどなかった。(中略)半年、いやもっとだろうか、鬱々として過ごした。毎日のように子供たちをアパートの近くの公園に連れて行き、明るい笑顔を、ぼんやりと暗い気持ちで眺めていた。/夏も終わりに近づいたある日、知り合いの編集者から電話があった。一年間の連載ルポをやらないかと言う。それも「職業で旅をしている人間に密着同行して日本中を歩く」のだと言う。僕は、跳び上がって喜んだ。(『人、旅に暮らす』301~302ページ「あとがき」)
足立さんは鳥取県出身、
自衛官のお父さんの転勤とともに
境から横須賀、川崎、佐世保と引っ越したり、
大学のころにアメリカと北欧を回ったり、
若い時代に「旅」があったのだそうです。
『日本海のイカ』もスルメイカの回遊を追いかけて旅したルポで、
また、
『1970年の漂泊』(文春文庫・1991年)
という自伝ノンフィクションも書いてます。
取材記者を辞め、生活の安定を捨てて、
足立さんは自分に合った取材の仕事を
やろうと決めてたんですね。
わたしはそう思います。
しばらく時間かかったけど、
自分のテーマが向こうからやってきた。
わたしも
しばらく待ってみようかな。
取材の仕事の自信は、まだないけど。
中坊公平さんの巻。
08/12/05
わたしの田舎は
福井の小浜というところです。
人口3万ほど、
のんびりした雰囲気の港町ですけど、
今年は、
NHKの連続テレビ小説「ちりとてちん」の舞台になったり、
アメリカのオバマ次期大統領さんのおかげで注目されたり、
にわかに盛り上がったみたいでした。
東京から帰省するときは、
京都経由で新幹線と電車を乗り継ぎます。
で、
せっかく京都を通るんだからと、
そこで1泊旅行してから帰るんです。
宿はいつも、
京都大学の近くの「聖護院御殿荘」。
この旅館が中坊公平さん経営なんですね。
中坊さんは
日本弁護士連合会の会長も務めた人で、
10年前の司法制度改革審議会では委員として、
現在の裁判員制度の導入をリードしたそうです。
整理回収機構の社長として
住専の不良債権処理に手腕を発揮していたころは、
「平成の鬼平」と呼ばれてメディアにひんぱんに登場したり、
首相候補に名前があがったりしました。
一見、
すごく偉い人で、
エリートなのかなと思いきや、
著書を読むとそんな感じはぜんぜんありません。
さっきの聖護院御殿荘も、
1泊1万円前後で利用できる気さくな旅館です。
中坊さんの初めての著書
『罪なくして罰せず』(朝日新聞社、1999年)に
こんな一節があります。
......私は大事に育てられた。子守役のお手伝いさんがいつも遊び相手になってくれて、父も母も私が寝小便を繰り返しても決して怒らなかった。だが、学校では落ちこぼれで、なかなか友達ができない。今でこそ一千枚近くの年賀状をもらうようになったが、その時代には一枚も来ないことがあった。私は孤独で、知らず知らず「自分は弱い人間なんだ」と自覚しながら大きくなったように思う。(同書107ページ)
司法試験は3回目でやっと合格。弁護士になってからも
仕事の依頼がぜんぜん来ない時期が
長くつづいたといいます。
でも、
やがて、
「裁判に負けない弁護士」と評判になって、
なんとかひとり立ち。
中坊さんは
「現場主義」に徹する独自の手法を体得したんです。
私は旧制中学の受験も高等学校の受験も滑った落ちこぼれで、もともと勉強嫌いである。しかし裁判では、相手方より現場を知り尽くし、裁判官より事案の本質を踏まえていれば勝てることを知っている。事案の本質と法律の条文を比べればどちらが強いか、軍配は必ず本質を知っている側に上がる。法律はあくまで裁判の「手段」でしかないからである。法律の論理だけで裁判官を説得することはできないが、現場の体験から弁論すれば納得してもらえる。(同書99ページ)
どんな事件を依頼されても
中坊さんはまず事件の現場を見聞きして回り、
その状況を肌で感じ、
ときにはそこで依頼人と一緒に
会食したりするのだと。
そういうふうに視覚から触覚、味覚まで、
つまり五感をすべて働かせると、
たいてい現場から
「事実の本質」
とでもいうべきものが見えてくるんだそうです。なるほど。
そんな現場主義を武器に
中坊さんは数々の大事件に挑み、
たくさんの被害者を救ってきました。
森永砒素ミルク中毒事件、
豊田商事事件、
香川県豊島の産廃不法投棄事件......。
なかでも
わたしがいちばんスカッとさせられたのが
「千日デパートビル火災裁判」での中坊さんです。
大阪・ミナミの繁華街にあった
「千日デパートビル」が焼けたのは
1972年5月13日の夜。
118人が死亡した
日本のビル火災史上、最悪の大惨事です。
中坊さんは
焼け出された千日デパートのテナントたち、
具体的には
化粧品や婦人服や宝石や靴といった
小さな店を営む36人から依頼を受けて、
ビルを所有するドリーム観光を相手に損害賠償を求めました。
当時、
ドリーム観光は奈良や横浜で遊園地を運営する大企業でしたが、
「千日デパートビル火災で防火上の手落ちはない」
「ビルは滅失したからテナントの賃借権もなくなった」
などと主張して、
化粧品や婦人服や宝石や靴の店主に、
つべこべいわず、あんたら出て行け、と。
中坊さん、
これに怒りました。
私は落ちこぼれで弱い子どもとして育ってきたせいか、横暴な強者を前にすると、とことん反発するところがある。私は勉強も運動もできず、十六歳まで寝小便をたれているような子どもだったが、ケンカをすれば負けなかった。殴り合いでは勝ち目はないから、相手の腕でも足でも服の上から噛みつくのである。いちど噛みついたら、叩かれようが蹴られようが、絶対に離れない。口の中に相手の血が滲んできても離さなかった。むしろ、その血は飲み込んだ。当然、相手はケガをして病院のお世話になった。寝小便には何も言わなかった母も、このときばかりは「公平さん、友達を傷つけてはいけません」と怒ったが、私には生来こうしたマムシのような闘争本能が宿っているのかもしれない。(同書103ページ)
中坊さんは裁判で猛烈に反論、
8年におよぶ長い闘いに勝訴します。
その詳しい経緯は書きませんが、
わたしは
千日デパートビル火災裁判の中坊さんの話で
弁護士とは何をする職業なのか
はっきりわかったんですね。
弱い人たちを助ける仕事なんだって。
中坊さんは毀誉褒貶の多い人でもあり、
住専処理にあたっていたころの債権回収をめぐって刑事告発され、
それをきっかけに弁護士を廃業して、
現在は旅館経営に専念されているそうです。
債権回収でどんな問題があったのか、
わたしにはわかりません。
ただ、
『罪なくして罰せず』の「はじめに」のなかで、
中坊さん、こう書いてるんですね。刑事告発される前の記述です。
私はこの三年間(住専処理にあたった三年間)、しばしば過激な姿勢で債務者や住専破綻の責任者と対決し、(整理回収機構の)社員たちには激励、号令、罵詈雑言を浴びせ続けて債権回収にあたってきた。冷静な指揮官というより頑固な職人みたいな仕事ぶりだったが、それに対する世間の毀誉褒貶はあまり気にしなかった。いま私には、私なりに納得のいく仕事ができたという充足感があるけれど、私のこの仕事が長い目で見て歴史の批判に耐えられるまっとうなものだったかどうか、その答えはすぐにはだせないからである。(同書2ページ)
中坊さんは来年で80歳。
わたしが帰省の途中に京都で1泊するのは
そこで偶然でもいいから
中坊さんに会えないかなあと願っているからです。
久田恵さんの巻。
08/10/17
中学2年と小学5年のふたりの娘に、
子育てというほど、たいしたことはしてません。
面倒なことは、ほとんど妻まかせ、
だめな父親だなあと思うだけで、なんにもしないんですけど、
3つだけ、
「けがと病気に気をつけるように」
「事故と事件にも巻きこまれないように」
それから、
「将来は仕事をもって、女性でも経済力をつけるように」
ということを、ときどき、いうようにしています。
娘たちは、
1つめ、2つめのことはともかく、
3つめのことは、あんまりピンとこない様子ですけど、
ま、大きくなってからピンとくればいいかと思って、
わたしの話をちゃんと聞いてくれそうなタイミングを見はからって
いいきかせてるんです。
そんなこという当のわたしの経済力が心もとないということは
たなにあげてますが。。。
で、
わたしが娘たちにそんなこというのは、
女性は、
男性よりもたくさん、
いろんなことを乗り越えなくちゃ仕事をつづけられない、
と思うからです。
いまのよのなか、
女性がずっと仕事をつづけて、
自力で生計を立てられるほどお金を稼ぐのは、まだまだたいへんだけど、
娘たちには、なんとかそれをやってみてほしいんですね。
久田恵さんは
ノンフィクションの書き手として、
『フィリピーナを愛した男たち』(文藝春秋)で
1990年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞、
いまもって活躍をつづけている女性です。
最近では、
『私の仕事 私の生き方』という文藝春秋の季刊誌(2007年)にも
「女と仕事――そして『定年』後」
という題でエッセイを発表しています。
思えば、私は団塊世代である。
同級生の男たちが、いよいよ定年期に突入して、これからなにをしようか、と考え始めているこの人生の節目に(フリーランスの私は定年とは無縁の立場だけれど)、一人の女として、「働いて、稼いで、自立して生きたことが誇りだ、後は、時々、楽しいことがあればもうなにもいらない」という境地に至っている自分に驚いている。(同書147ページ)
もちろん、
久田さんがいまにいたるまでには、
山あり谷ありだったと思います。
久田さんは
ノンフィクションの仕事をなりわいとするまでに、
あれやこれや、いくつも仕事を経験してるんです。
......そう、思い出すのも大変なほど、私はさまざまな仕事をして生計を立ててきたのだった。
その「変転」は、「素手で、自力で、人生を切り開く!」と、一通の書き置きを残して家出をした二十歳の時から始まった。
つまりは、女がそんな無謀なテーマを持ってしまうと、めまいがするほどめまぐるしく生きざるを得ないわけで、私はそんな世代の女の一人だったのである。
トランジスター工場の女子工員に始まり、ウエイトレス、パン屋の店員、スーパーの試食販売、人形劇団員、フリーの人形遣い、放送ライター、東販の伝票整理、区役所のアルバイト、家庭教師、知人の家の賄い、キャバレーの衣装係、舞台照明の助手、業界雑誌記者、広告会社嘱託、サーカス団の炊事係、女性誌ライター......。
どう考えても、行き当たりばったり。
脈絡がない。ほとんど闇雲である。(同書146ページ)
でも、
面白いのは、
いろんな仕事を転々とするなかでも、
若い久田さんがへんに落ち込んだりせずに、
すごく元気に毎日を暮らしていたんじゃないかと
思えることです。
久田さんが仕事を転々としていたのは、
高度成長時代の終わりのころですけど、
もし、いまの若い人たちが、
こんなふうにころころと仕事をかえて暮らしているとなると、
将来不安がどうとか、最低賃金がこうとか、
なんとなく暗い感じになっちゃうんじゃないでしょうか。
久田さんは暗い感じで仕事を転々としてなかった、
ということがわかるのは、
たとえば、
エッセイ集『愛はストレス』(文藝春秋、1996年)で、
その仕事のなかみについて、
こんなふうに披露しているからです。
ふと思いついて人形劇団をつくり......埼玉や千葉などを地図を片手に車で走り、保育園や幼稚園を見つけると、車を止めて訪問し、園長先生に「子どもたちに夢を」などと言って仕事をとるのである。
私立の保育園や幼稚園の園長先生には基本的に人柄の良い人が多い。
「まあ、お若いのに......」
「素敵なお仕事ですこと」
などと言って、ともかく話を聞いてくれて、一日回ればなんとか二つ、三つの園で「一公演、二万円から一万五千円」の仕事の契約がとれたのである。......儲かりはしなかったが、なんというか遊んでいるような働いているような、そんなわけのわからないお金の稼ぎ方が実に良かったのである。(同書86~87ページ)
そんな久田さんも、
子どもが生まれてから、
どうやって仕事をつづけるか、つづけないのか、
ずいぶん悩んだ時期があったそうです。
初めての著書
『母親が仕事をもつとき』(学陽書房、1982年)
を書き終えたとき、
久田さんは夫と別れ、
ひとりで働きながら子どもを育てることになった
といいます。
私はフリーのライターという不規則な仕事をしていたこともあり、保育園だけではとてもおさまらず、一時は、友人、知人、ベビーシッター、と子どもを預けまくって育てた。
「おかあさん、今日は、ボクをどこに預けるの?」
そう聞いた幼い息子の声が、いまも聞こえるようで、子どもの情緒が少しでも不安定になったりすると、あの時、この時のあれこれを思い出し、きっと私が悪いんだ、と罪悪感にさいなまれたことも多かった。それは、働く母親なら誰でも経験する心境でもあるが、この内面化された「母性神話」から私もなかなか解放されなかったのである。(同書文庫版あとがき、296~297ページ)
それでも、
息子さんが12歳の中学生になったとき――
入学祝のCDプレーヤーでビートルズなんか聞いている彼の横顔を見ていたら、ふと、長かった子育ても一段落したなあ、と肩の荷が少し下りたような気がして、ふと、言ってみたことがあった。
「ねえ、おかあさんはずっと仕事をしていて、小さい時からあなたにずいぶん苦労かけたのよね」
その時である。息子はビートルズを聞きながらのどかに答えたのだった。
「小さい時の苦労なんか覚えてないよ。だけど、ボク、おかあさんと一緒で結構、面白かった」
その「面白かった」の一言がどれほど胸にしみたことか。(同書文庫版297ページ)
わたしは
久田さんに取材で合計4回、
お目にかかったことがあります。
3年前、
4回目の取材のときにいただいた名刺には、
片面にお名前だけ、
ひっくり返すと、
ご自宅の住所とともに
「花げし舎」
と刷ってありました。
久田さんが自宅を拠点に「花げし舎」を主宰して、
人形のお芝居の公演をしたり、
いろんなことをいろんな人たちと
はじめたんですよと、
楽しそうにおっしゃっるので、
わたしも楽しい気持ちになって、
自分もなにかはじめてみようと思ったのでした。